「60代から新NISAを始めるのは遅いのではないか」
そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか?
結論、60代から新NISAを始めても、全然遅くありません。
「今から始めても意味があるの?」と疑問に思う方も多いかもしれませんが、適切な方法で運用すれば老後資金を安全に増やすことは十分可能です!
本記事では、60代からでも取り組める新NISAの賢い活用方法について、徹底解説します。
リスクを抑えつつ、老後資金を安全に増やすための具体的な方法や注意点を学びましょう。

安心したセカンドライフを送れるように資産形成していきましょう!
60代から新NISAを始めるのは遅い?
うまく運用できれば、決して60代から新NISAを始めても遅くありません。
確かに、これまでのNISAは運用期間に制限があり、長期投資が基本とされていました。
しかし、2024年から始まった新NISAでは、非課税で保有できる期間が無期限になったため、ご自身のライフプランに合わせて自由に運用できるようになりました。
例えば、退職金などのまとまった資金を使い、非課税で効率的に資産を増やすことも可能です。
以前の制度よりも柔軟性が高まり、60代の方にも利用しやすい制度になっていますので、新NISAを始める60代の方も増えています。
60代で新NISAを活用すべき4つの理由
60代から新NISAを始めるには、上手く活用することが大切です。
ここでは、4つの活用すべき理由を解説していきます。
- 非課税保有できる期間が無期限になった
- 予想以上に老後費用が必要になる
- インフレで金融資産が目減りする
- 定年後の再就職で収入が減る
非課税保有できる期間が無期限になった
2024年から始まった新NISAは、非課税で投資できる期間が無期限になりました。
これにより、60代からでも焦らずに長期的な視点で資産運用に取り組めます。
旧NISAでは最長20年という制限がありましたが、新NISAではご自身のライフプランに合わせて好きなタイミングで売却が可能です。
この柔軟な制度を活用すれば、退職金などのまとまった資金を有効に増やせるでしょう。
予想以上に老後費用が必要になる
60代から新NISAを始めるべき理由のひとつに、老後資金が予想以上にかかる点が挙げられます。
健康寿命が延び、人生100年時代といわれる現代では、老後の生活期間が長くなるため、それだけ多くの生活費が必要です。
公的年金だけでは不足する可能性も高く、ゆとりのあるセカンドライフを送るためには、現役時代からの計画的な資産形成が重要になります。
新NISAを活用して、効率的に老後資金を準備していきましょう。
インフレで金融資産が目減りする
物価が上昇するインフレ下では、現金の価値は相対的に下がってしまいます。
たとえば、100万円で買えたものが翌年には110万円出さないと買えない、といった状況が起こるのがインフレです。
銀行に預けているだけではお金はほとんど増えないため、知らないうちに資産が目減りするリスクがあるのです。
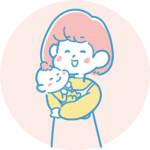
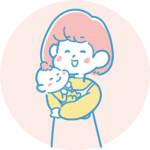
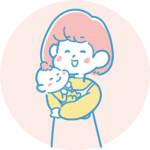
新NISAを活用すれば、効率的に資産を増やしながらインフレ対策もできますよ。
定年後の再就職で収入が減る
定年後に再雇用されたり、再就職したりする場合、現役時代と比べて収入が減少するケースがほとんどです
役職手当などがなくなり、給与体系が変わるためです。
支出を減らす工夫も重要ですが、それに加えて、新NISAを活用して資産を増やし、公的年金だけでは不足しがちな生活費を補うことが大切になります。
老後の生活の安定を目指す上で、新NISAは有効に活用し資産形成をしていきましょう。
老後に必要なお金の内訳
60代で新NISAを始める前に、老後にいくら必要になるのか知っておく必要があります。
定年後の生活費や年金の平均額など老後のお金について詳しく解説します。
定年退職後の生活費と貯金額
定年退職後の生活費について、具体的に見ていきましょう。
総務省の家計調査報告(令和5年)によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、年金などの実収入が月額約24.5万円なのに対し、消費支出は約25.1万円。毎月およそ6,000円の赤字が発生しています。
一方で、65歳以上の単身無職世帯では、実収入が約12.7万円に対し、消費支出は約14.5万円で、月額約1.8万円の赤字です。
これらのデータから、多くの世帯で毎月貯蓄を取り崩して生活していることがわかります。
次に、60代の貯蓄額はどうなっているのでしょうか。
金融広報中央委員会の家計調査(令和5年)によると、60代の金融資産保有額の平均値は、二人以上の世帯で約2,588万円、単身世帯で約2,240万円となっています。
金額はあくまで平均値であり、中央値(より実態に近い値)はそれぞれ約1,200万円、約1,100万円です。
これらの貯蓄を毎月の不足分に充てていくと、貯蓄の寿命(いつまで資産がもつか)が課題となります。
公的年金に加えて、新NISAのような制度を活用して計画的に資産を形成すれば、貯蓄を少しでも長持ちさせることが可能です。
貯蓄をただ取り崩すだけでなく、資産を増やしながら暮らすことで、より安心した老後生活を送れるでしょう。
年金と退職金の平均額
老後の生活を支える年金と退職金について見ていきましょう。
年金の平均額は、日本年金機構 日本年金機構の主要統計(令和4年度版) によると、国民年金(自営業者など)の平均受給額は月額約5.5万円です。
一方、厚生年金(会社員など)の平均受給額は月額約14.5万円となっており、国民年金のみの人と比べると大きな差があります。
次に退職金の平均額ですが、りそなグループの調査によると、大学・大学院卒の退職金平均額は20年以上勤続で約1,940万円です。
ただし、退職金は勤続年数や企業の規模によって大きく変動します。
例えば、大企業と中小企業では退職金額に大きな開きがあります。
これらの平均額はあくまで目安として、ご自身の年金や退職金がどのくらいになるかを確認し、老後資金の計画を立てる際の参考にしてください。
老後にいくら必要?生活費のシミュレーション
老後に必要な金額は、個人の生活スタイルや状況によって大きく異なりますが、一般的なケースでシミュレーションしてみましょう。
夫婦世帯の老後のシミレーション(夫が厚生年金、妻が国民年金を受給)
- 生活費の目安: 月額286,877円(総務省「家計調査報告 平均結果の概要」版2024年(令和6年)版より)
- 年金受給額の目安: 月額約20.0万円(厚生年金約14.5万円+国民年金約5.5万円)
- 毎月の不足額: 約8.2万円
この不足分を65歳から20年間補うには、およそ1,968万円の貯蓄が必要になります(8.2万円 × 12ヶ月 × 20年)。
単身世帯の老後のシミレーション(国民年金を受給)
- 生活費の目安: 月額161,933円(総務省「家計調査報告 平均結果の概要」版2024年(令和6年)版より)
- 年金受給額の目安: 月額約5.5万円(国民年金のみ)
- 毎月の不足額: 約10.1万円
この不足分を65歳から20年間補うには、およそ2,424万円の貯蓄が必要になります(10.1万円 × 12ヶ月 × 20年)。
これはあくまで平均的な生活費で計算した目安です。
ゆとりのあるセカンドライフを望むなら、さらに多くの資金が必要になるでしょう。
このように、公的年金だけでは生活費が不足する可能性が高く、そのギャップを埋めるための資産形成が非常に重要です。
新NISAを活用すれば、効率的に資産を増やし、ご自身のライフプランに合わせた「資産寿命」を延ばすことにつながります。
ご自身の年金受給額や生活費を具体的に計算し、必要な老後資金を把握したうえで、新NISAを賢く活用していきましょう。
60代が新NISAを始めるときの3つのポイント
60代が新NISAを始める際のポイントを3つにまとめて紹介します!
- いつどれだけのお金がかかるか計画を立てる
- 一括投資ではなく積立投資を行う
- リスクを考えて分散投資を行う
いつどれだけのお金がかかるか計画を立てる
60代から新NISAを始める際は、まず今後のライフプランを具体的に描き、いつ、どれくらいのお金が必要になるかを計画することが大切です。
これにより、すぐに使うお金と、しばらく使う予定のないお金を明確に分けられます。
老後の生活費はもちろん、住宅のリフォーム代や車の買い替え費用、旅行、医療費など、将来かかるであろう大きな支出をリストアップしてみましょう。
例えば、「65歳で退職し、70歳までは旅行を楽しむ資金が必要。75歳で自宅のリフォームを考えている」といった具体的な計画を立てることで、それぞれの支出に必要な金額と時期がはっきりします。
計画をもとに、すぐに使う予定のお金は預貯金として確保し、数年後や十年後に使うお金を新NISAで運用する、といったように資金を振り分けましょう。
一括投資ではなく積立投資を行う
退職金などのまとまったお金がある場合、一括で投資するのではなく、積立投資を活用した資産運用がおすすめです。
定年退職後は、毎月の収入が減るため、積立投資の元となる資金を確保しておく必要があるからです。
また積立投資の場合、投資のタイミングを分散させることで価格変動のリスクを抑えられるというメリットもあります。
この方法は、ドルコスト平均法と呼ばれ、価格が安いときには多く、高いときには少なく購入するため、購入価格を平準化する効果があります。
退職金をただ預金しておくのではなく、新NISAの積立投資枠を上手く利用することで、時間をかけて効率的に資産を増やせるでしょう。
ただし、元本保証のない商品もあるため、一部は安全性の高い資産で保有しておくことも重要です。
リスクを考えて分散投資を行う
60代から新NISAを始める際は、分散投資を意識することが大切です。
ひとつの資産に集中して投資すると、その資産の価値が大きく下がった場合、資産全体に大きな損失を被るリスクが高まります。
分散投資には主に3つの方法があります。
資産の分散:株式だけでなく、比較的リスクの低い債券や不動産にも投資する
地域の分散:日本国内だけでなく、先進国や新興国の株式にも投資する
時間の分散:一度にまとめて投資するのではなく、毎月少しずつ積み立てていく
これらの分散を組み合わせることで、特定の資産や地域の価格変動の影響を受けにくくなり、リスクを抑えながら安定的に運用できます。
新NISAの「つみたて投資枠」では、最初から複数の資産や地域に投資する「バランス型ファンド」など、分散投資に適した商品が厳選されています。そのため、初心者の方でも安心して始めやすいでしょう。
60代から新NISAを始める際の4つの注意点
運用年数が確保しにくい
60代から新NISAを始める際の注意点として、20代や30代世と比べて運用年数が確保しにくいことが挙げられます。
投資は長期で運用するほど、値動きのブレが小さくなり、安定的な利益を得やすくなるのが一般的です。
しかし、60代では運用できる期間が限られるため、若い世代と同じようなリスクの高い運用は避けなければなりません。
また、運用期間が短いと、投資したお金が元本割れしてしまう可能性も高くなります。
ご自身の資産状況やライフプランを考慮し、リスクを抑えた運用を心がけましょう。
定年後の収入減りで積立額が増やしづらい
定年後、再雇用制度などを利用して仕事を続ける場合でも、現役時代と比べて収入が減少するケースがほとんどです。
このため、毎月の家計から新NISAの積立額を増やすことが難しくなる場合があります。
生活費を年金で賄うようになると、自由に使えるお金も限られてくるため、無理な積立設定は家計を圧迫する可能性があるので注意が必要です。
そのため、積立金額は無理のない範囲で設定し、生活防衛資金は確保しておくようにしましょう。
また、退職金などのまとまったお金を元手に新NISAを始める場合も、将来の生活費や予期せぬ出費に備えるため、一部は現金として手元に残しておくことが大切です。
短期間で売買せず長期的な運用する
新NISAは、短期的な売買で利益を狙うのではなく、長期的な視点での運用が大切です。
資産運用を始めたばかりの頃は、日々の値動きが気になって、価格が上がったときに利益確定のために売却したり、下がったときに不安になって売却したりしたくなるかもしれません。
しかし、短期的な値動きに一喜一憂せず、落ち着いて運用を続けることが重要です。
特に「つみたて投資枠」は、毎月決まった金額を自動で積み立てていくため、価格が高いときは少なく、価格が安いときは多く購入できます。
これを「ドルコスト平均法」といい、長期的に見ると購入価格を平準化する効果があります。
この仕組みを活かすためにも、目先の利益や損失に惑わされず、長期的な運用を続けることが、60代から新NISAを始めるうえで重要なポイントです。
資産を維持することを目標にする
60代から新NISAを運用するのであれば、大きく増やすことよりも資産を減らさないことを目標にしましょう。
若い世代のように積極的なリスクを取るよりも、安定的な運用を重視することが重要です。
この時期の資産は、老後の生活を支える大切な資金なので、元本割れのリスクを極力抑える運用を心がけましょう。
まとめ
60代から新NISAを始めるのは遅くないという結論を軸に、その具体的な活用方法と注意点を解説しました。
新NISAは非課税期間が無期限になったため、長期的な視点で資産形成を目指せる非常にメリットの大きい制度です。
ただし、老後資金として運用するためには、ご自身のライフプランに合わせた資金計画を立て、リスクを抑えた分散投資を意識することが大切です。
また、短期的な売買は避け、資産を減らさないことを目標に運用を継続することが成功の鍵となります。
まずは無理のない範囲で始め、将来の不安を解消していきましょう。
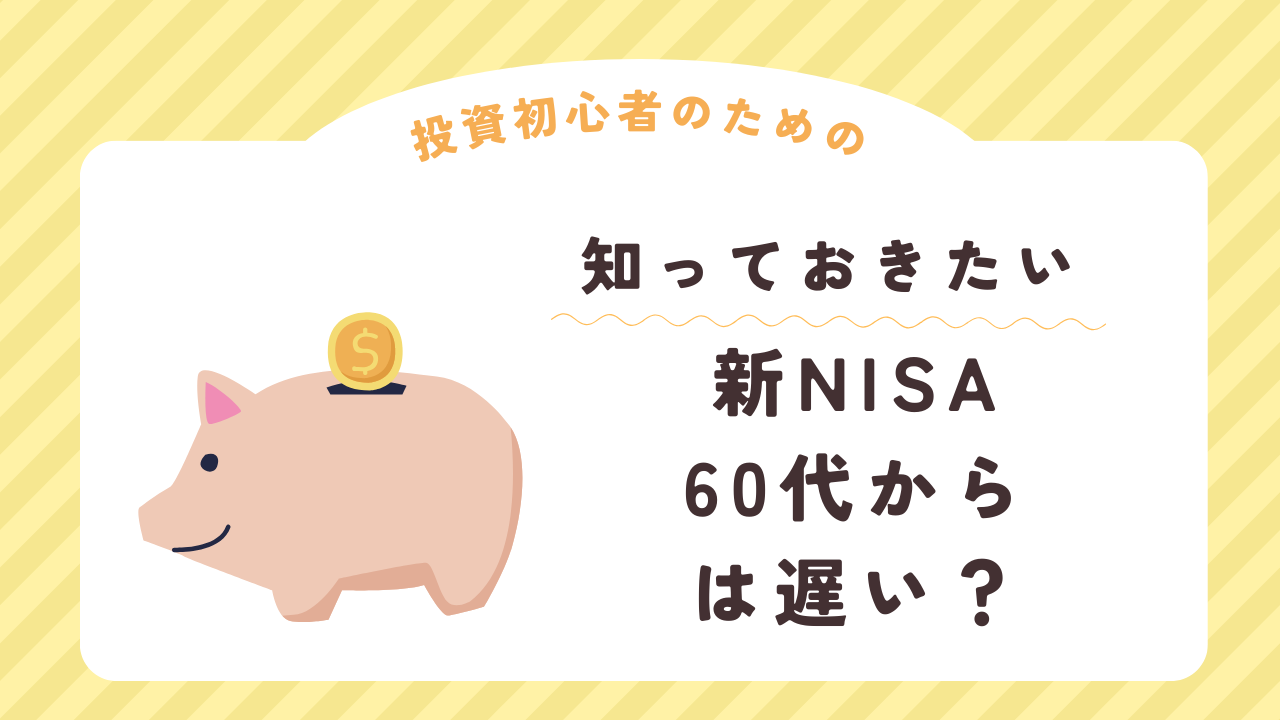

コメント